登山者として伊吹山に登ったとき、ふと頭をよぎる疑問がある。 「なぜこの山が、日本武尊(やまとたけるのみこと)の最期の地なのか?」 「奈良には八経ヶ岳のような高くて霊的な山もあるのに、なぜ伊吹山?」
たしかに奈良には古くから修験道の霊山が数多く存在する。だが、古事記や日本書紀に記される神話の構造を考えると、当時の日本神話は「大和の国」を中心に編まれた歴史叙述でもあったという前提を忘れてはならない。
その答えは、神話の構造と、自然に対する日本人の感覚の中にある。
荒ぶる神の山としての伊吹山
伊吹山は、標高こそ1,377mだが、日本屈指の豪雪地帯として知られ、強風「伊吹颪(おろし)」や氷雨といった自然の猛威にさらされてきた。古代においては、こうした自然現象は神そのものとされ、伊吹山は「荒ぶる神の山」として畏れられていた。
英雄・日本武尊(やまとたけるのみこと)は、東国を平定した帰路に伊吹山の神を討とうとするが、その神の化身とされる白い大猪を侮り、神の怒りを買う。氷雨を浴びて病を得た尊は、伊勢(いせ)の能煩野(のぼの)で命を落とす。この神話は、古事記に記された話である。
伊吹山が“最期の地”に選ばれた理由
奈良の八経ヶ岳の方が高く、古くから修験道の聖地でもある。しかし、伊吹山には神話的な「最期の舞台」としての要素がそろっている。
- 都(奈良・大和)から見て、東国との結界に位置する場所
- 自然災害の象徴的存在であり、神の怒りを感じさせるにふさわしい
- 畏れを忘れた英雄が試され、命を落とす舞台として適していた
つまり、伊吹山は“英雄の力でも超えられなかった自然そのもの”として描かれた山だったのだ。
なぜ侮ったのか ― 慢心と敗北
日本武尊(やまとたけるのみこと)は、多くの戦いに勝ち続け、東国でも火攻めを切り抜けるなど数々の武勇を見せていた。 伊吹山に現れた白い猪は、神の使いとわかっていたのに、「取るに足らない」と侮った。
これは、英雄としての「慢心」と、それを試す「神の化身」という構造であり、 「人の限界」「自然の絶対性」を示すために必要な敗北だった。
敗れた者を祀るという日本的信仰
日本では、非業の死を遂げた者を神として祀り、土地の神、守り神として鎮める文化がある。 伊吹山に日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀るのも、荒ぶる神を直接祀るのではなく、神に敗れた者を祀ることで、神を和らげるという信仰構造の表れだ。
だから伊吹山は、ただの敗北の舞台ではない。 人が神に出会い、敗れ、そして祈りの対象となった場所なのだ。
伊吹山で祈るということ
伊吹山は、勝利を願う山ではない。 むしろ、自分がうまくいっているときほど、登るべき山かもしれない。
調子に乗りそうなとき、周囲への感謝を忘れかけたとき、 この山に登り、立ち止まり、手を合わせる。
「今の自分があるのは、自然の恵みと、人の支えのおかげです。 おごらず、丁寧に、進んでいきます。」
そんな祈りが、伊吹山にはよく似合う。
日本武尊(やまとたけるのみこと)は、かつてスサノオ命が八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したときに得た草薙剣(くさなぎのつるぎ)を授かっていたとされる。神の力を宿すその剣を継ぎ、その剣で荒ぶる伊吹山の神に挑んだが、神そのものを越えることはできなかった。 それでも、その魂は白鳥となり、空へと飛び立った。
伊吹山は、敗れた者を責めない。むしろ、 その敗北から学び、次へ進む者を見守ってくれる山なのだ。




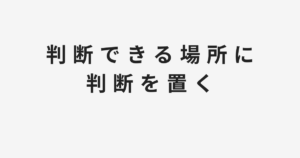





コメント